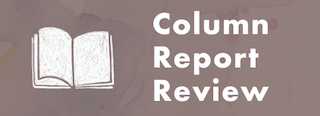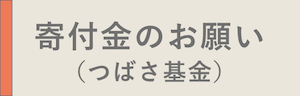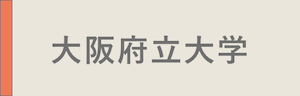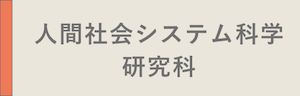コラム/レポート/レビュー
category
第23期女性学講演会第2部「文学とジェンダー」報告
2019年12月21日(土)、I-siteなんばで第23期女性学講演会第2部「文学とジェンダー」が開催されました。以下、簡単に報告いたします。
 暮も押し迫った12月末での開催でしたが、大勢の方々に参加して頂きました。今回は、「男性作家は女性をどのように描いたのか」というテーマのもと、慶応義塾大学の小倉孝
暮も押し迫った12月末での開催でしたが、大勢の方々に参加して頂きました。今回は、「男性作家は女性をどのように描いたのか」というテーマのもと、慶応義塾大学の小倉孝 誠先生をお招きし、19世紀から20世紀にかけてのフランス文学における女性の表象を探りました。
誠先生をお招きし、19世紀から20世紀にかけてのフランス文学における女性の表象を探りました。
まず、村田が19世紀後半の自然主義作家ゴンクール兄弟の芸術小説『マネット・サロモン』(1867) を中心に、バルザックの『知られざる傑作』(1831) とゾラの『制作』(1886) とも比較しながら、男性作家と女性モデルの関係をジェンダーの視点から検証しました。19世紀における芸術小説では、男の画家の創造の苦しみが描かれると同時に、画家と女性モデルとの恋愛関係が描かれています。バルザックとゾラの小説では、画家は女性モデル(=恋人)への「欲望の眼差し」と、冷徹な「画家の眼差し」との間で揺れますが、最終的には「画家の眼差し」を優先し、女性は芸術の犠牲となります。それに対して、『マネット・サロモン』では男の画家が女のモデルによって、その画家人生を破壊される物語です。それは、マネットが他のヒロインとは違い、職業モデルとして、自らが芸術家の創造行為に寄与していることを誇りにしていること、さらに、彼女が自らの肉体によって作品を「制作」する創造者に変貌していること、によるものです。とりわけ女性が創造行為の主体と対象を兼ねる点に、ジェンダー的反転が見出せます。物語の最後でマネットが母親になると、貪欲な「ユダヤの女」に変貌して画家の才能、人格すら解体していきます。そこには作者の反ユダヤ主義が色濃く反映されていますが、小説の醍醐味は、マネットが自らの裸体を鏡に映しながら、「作品」を制作する場面にあると言えるでしょう。この小説は、シャセリオーの《エステルの化粧》やレンブラントの《夜警》など、絵画が大きな役割を果たしているのも大きな特徴となっています。
 小倉先生のご発表「若い女性たちの表象と現実」は、19世紀から20世紀にかけてのフランスの男性作家たちが描いた「若い娘 (jeune fille)」の特徴および、同時代の文化、思想との関連を探るものです(写真は講演中の小倉先生)。とりわけ3つの時代――19世紀前半のロマン主義文学、19世紀後半のリアリズム・自然主義文学、1920年代の文学――に分けて、それぞれの時代の代表作における若い娘の表象を分析されました。まず、『ポールとヴィルジニー』や『ルネ』などロマン主義文学では、若い娘は身体性が希薄で、「天使的」な女性として描かれていたのが、リアリズム・自然主義文学(エドモン・ド・ゴンクールの『シェリ』)になると、医学的言説(男性の医者による)に基づき、若い娘は「生理学的存在」とみなされ、女の身体と病理に対して鋭い視線が投げかけられるようになります。ただ、ゴンクールに関して興味深いのは、これまでの文学では男性から見た女性像であったのが、作者が女性の回想録や手紙、日記など女性自身の証言をもとに「女性性」を描いている、ということです。『シェリ』には少女から女に変わる「月経」という現象が、医学的言説を交えながら詳細に描写されていますが、こうした描写はロマン主義文学には絶対に見出せないものです。さらに、「狂乱の歳月 (Années folles)」と呼ばれた1920年代の小説、マグリットの『ギャルソンヌ』では、女主人公が経済的に自立し、身体的にも解放されていること(スポーツ的身体)、性愛体験においてもタブーを破ることによって、解放された「新しい女性」が描かれています。1920年代はヘミングウェイやフィッツジェラルドなど「ロスト・ジェネレーション」と呼ばれた作家の時代であり、まさにフィッツジェラルドの妻ゼルダや『華麗なるギャツビー』に登場するデイジーのように、短髪で性的にも奔放な女性が登場します(小倉先生の講演の最後に、その時代を描いたウッディ・アレンの映画の一部が上演され、会場も盛り上がりました)。
小倉先生のご発表「若い女性たちの表象と現実」は、19世紀から20世紀にかけてのフランスの男性作家たちが描いた「若い娘 (jeune fille)」の特徴および、同時代の文化、思想との関連を探るものです(写真は講演中の小倉先生)。とりわけ3つの時代――19世紀前半のロマン主義文学、19世紀後半のリアリズム・自然主義文学、1920年代の文学――に分けて、それぞれの時代の代表作における若い娘の表象を分析されました。まず、『ポールとヴィルジニー』や『ルネ』などロマン主義文学では、若い娘は身体性が希薄で、「天使的」な女性として描かれていたのが、リアリズム・自然主義文学(エドモン・ド・ゴンクールの『シェリ』)になると、医学的言説(男性の医者による)に基づき、若い娘は「生理学的存在」とみなされ、女の身体と病理に対して鋭い視線が投げかけられるようになります。ただ、ゴンクールに関して興味深いのは、これまでの文学では男性から見た女性像であったのが、作者が女性の回想録や手紙、日記など女性自身の証言をもとに「女性性」を描いている、ということです。『シェリ』には少女から女に変わる「月経」という現象が、医学的言説を交えながら詳細に描写されていますが、こうした描写はロマン主義文学には絶対に見出せないものです。さらに、「狂乱の歳月 (Années folles)」と呼ばれた1920年代の小説、マグリットの『ギャルソンヌ』では、女主人公が経済的に自立し、身体的にも解放されていること(スポーツ的身体)、性愛体験においてもタブーを破ることによって、解放された「新しい女性」が描かれています。1920年代はヘミングウェイやフィッツジェラルドなど「ロスト・ジェネレーション」と呼ばれた作家の時代であり、まさにフィッツジェラルドの妻ゼルダや『華麗なるギャツビー』に登場するデイジーのように、短髪で性的にも奔放な女性が登場します(小倉先生の講演の最後に、その時代を描いたウッディ・アレンの映画の一部が上演され、会場も盛り上がりました)。
講演の後の討論の場でも、活発な質疑応答がなされ、盛会のうちに終わりました(参加者70名)
(コーディネーター 村田京子)